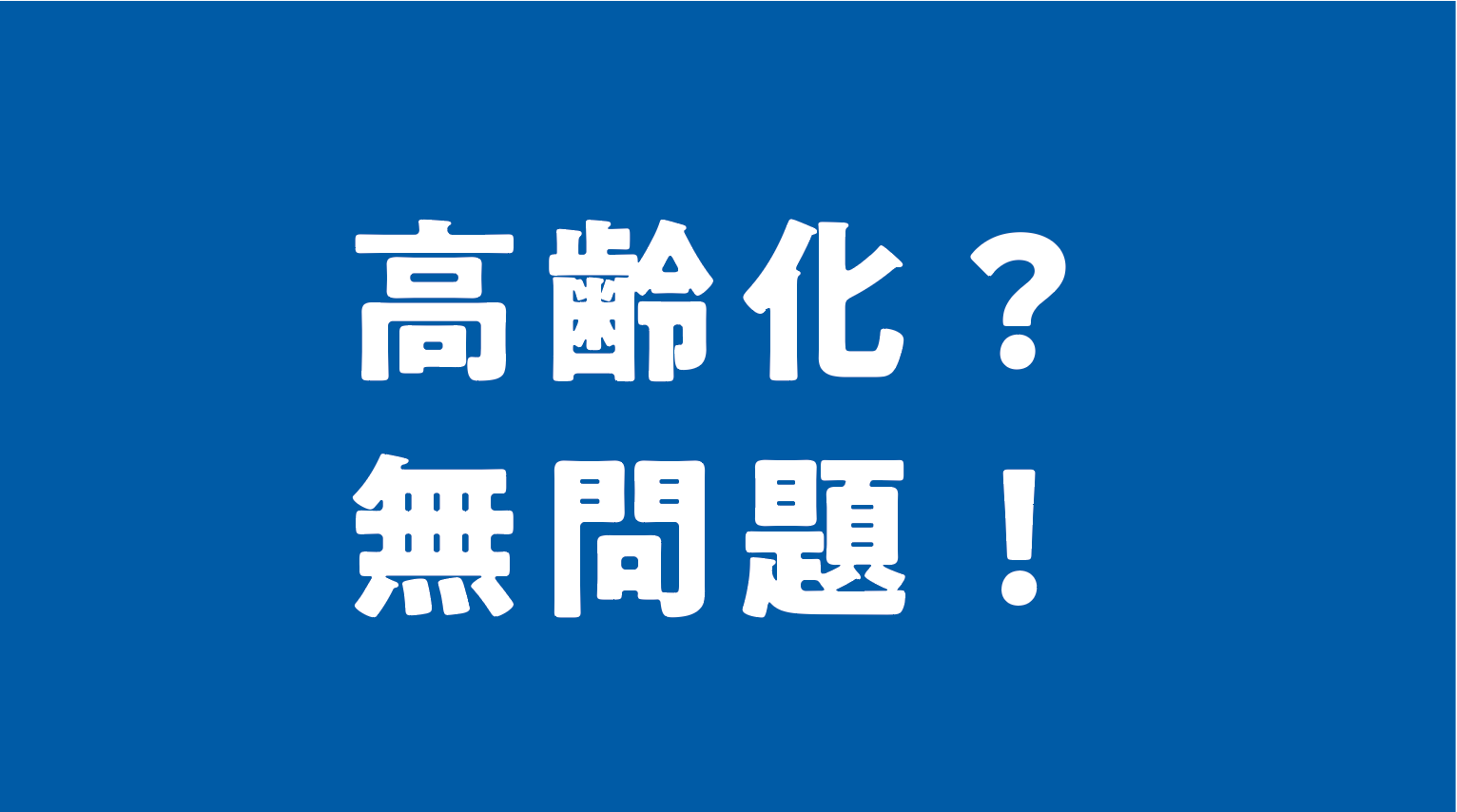仕事(会社)を定年退職後、ヒマで、趣味を探し始める人がまだまだ多いそうです。
そんなみなさまには身体と頭をそこそこ使う「さかな釣り」なんていかがでしょうか?
大阪の公認釣りインストラクター団体であるJOFI大阪の会員数はかつて、200名を超えていたそうですが、現在は50名弱で落ち着いています(2025年6月現在)。
会員の年齢層は、正式に調べたわけではありませんが、60歳以上が7割近くを占めているのでは?
実際、釣り教室などの活動に積極的に参加しているのはほぼ60歳以上で、70歳代も多く、60前の私などはここではまだまだ若手。まさに日本の縮図、いや、日本など足元にも及ばない超高齢化団体です。
本日は、JOFI大阪をとおして日本の超高齢化社会をFISHTHINK(考えよう)、といった主旨ではなく、
高齢なんて問題ない、いや、むしろ良いではないか的なお話です。
釣りはよく一生の趣味と言われます。たとえ足腰が歳と共に衰え、足場の悪い波止や磯などに長時間立ち続けるのが辛くなったとしても、船に乗っての沖釣りなどであれば満喫できます。
歳と共に釣りものを変えていけば末長く楽しめ、長く楽しめば楽しむほど、釣りの技術の蓄積はもとより、それ以外のさまざまな体験をする機会も多く、知識や知恵が無意識のうちに貯まります。この現場から得た知識や知恵には唯一無二の価値があると、JOFIの活動を通して実感しています。
たとえば、釣り教室などで釣りを始めたばかりの方々に安全のお話をする際にはリアリティをもって、水の怖さを深く伝えることができます。ゴミ問題など釣り場の環境保全についても、自身の目で見た具体的な内容を伝えることができます。
話を聴く側にとっても話の内容に身近な感覚が湧くのか、興味を持って聴いていただけているようです。
「次世代への釣り文化の継承」
これはJOFIの活動趣旨のひとつです。なんとも大層な話のように聞こえますが、釣り文化とは社会的なと言うよりも、「釣り人ひとりひとりが体験をとおして得た技術、知識、知恵」であると考えればどうでしょう。
“経験の深い釣り人は、釣り文化そのものだ”と。その釣り人が、釣り歴の浅い方々に、さかなの釣り方はもちろん、安全や環境なといった釣りにまつわるあらゆることを自身の経験から得た言葉で伝えていく。釣り文化の継承とは、そんなとても小さな単位でコツコツとおこなう取り組みの集大成なのだと思う今日この頃です。そしてそれは、釣り歴のやたら長い、経験豊富な高齢インストラクターだからこそできる役割なのだと思います。
だから、JOFI大阪の高齢化、ばんざい!
今回は、そんなところで。
P.S. 「ばんざい!」とはいえ、JOFIの活動維持のためには若いに越したことはないのですが…。